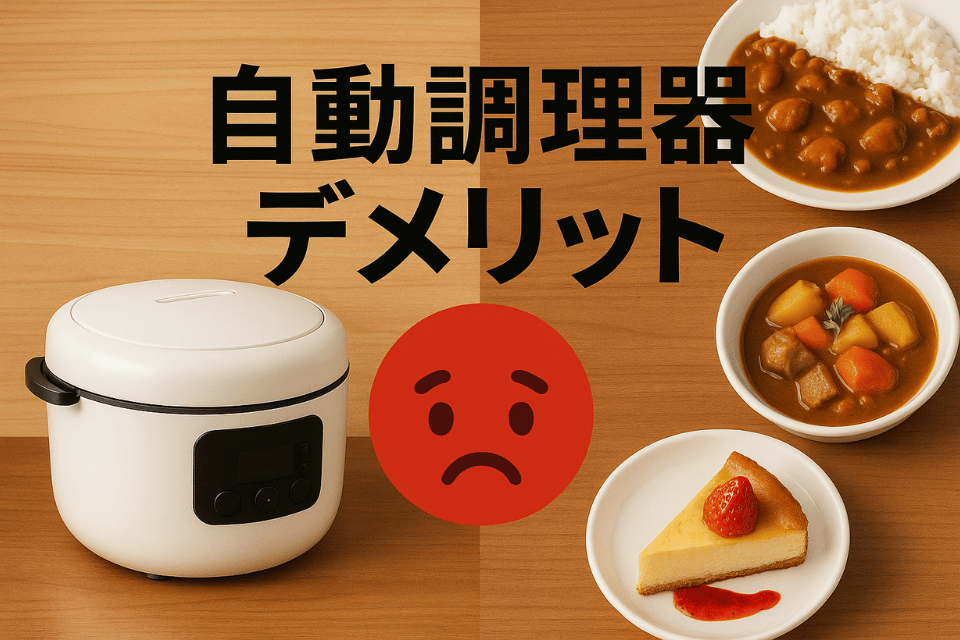「自動調理器って本当に便利なの?」「買って後悔したくない…」
そんな疑問を抱く人は多いでしょう。SNSや口コミでは、「便利だけど手入れが面倒」「思ったより大きい」など、デメリットも話題になっています。
本記事では、「自動 調理 器 デメリット」というキーワードに基づき、購入前に知っておきたい注意点と、後悔しない選び方を徹底解説。
象印やパナソニックなど人気メーカーの実例も交えながら、“失敗しないためのポイント”をわかりやすくまとめました。
読めばきっと、「買って良かった!」と思える1台の見つけ方がわかります。
自動調理器のデメリットとは?意外と知らない6つの落とし穴
お手入れが面倒?毎回の洗浄ポイント
自動調理器の一番のデメリットとしてよく挙げられるのが「お手入れの面倒さ」です。自動で調理してくれるとはいえ、使った後はどうしても洗浄が必要です。特に、圧力弁やパッキン、内ぶた、内鍋など複数のパーツがあるモデルでは、毎回すべてを取り外して洗う必要があります。煮込み料理などを作った後は油汚れやにおいが残りやすく、しっかり洗わないとカレーの香りが翌日まで残ってしまうこともあります。
象印の「EL-NS23」などは洗うパーツが3点のみと少なく設計されており、比較的手入れが簡単。しかし、他社製品では5〜6パーツある場合も多く、食洗機が使えない部品もあります。また、フタの内側やゴムパッキンの隙間に汚れが溜まりやすく、定期的に分解清掃が必要です。
こうした手間を減らすには、「食洗機対応」「パーツが少ないモデル」を選ぶことがポイントです。長期的に使うなら、調理の自動化だけでなく「洗う手間の自動化」にも注目して選ぶと後悔しにくくなります。
意外と時間がかかる?「時短」とは限らない理由
「自動調理器=時短家電」と思われがちですが、実は“すべての料理が早く終わる”わけではありません。理由は、圧力が上がるまでの予熱時間や減圧にかかる時間が想像以上に長いためです。例えば、電気圧力鍋でカレーを作る場合、実際の加圧時間は10分ほどでも、予熱+減圧を含めると合計40〜50分かかることがあります。
また、調理中にフタを開けて味見をしたり、途中で具材を追加したりすることができない点もデメリットです。「煮詰まり具合を見ながら調整したい」というタイプの人には、ややもどかしく感じるでしょう。
ただし、火のそばにいなくても安全に調理が進むというメリットがあるため、「時間の有効活用」という意味では十分に時短効果があります。ポイントは「調理時間」ではなく「手が離せる時間」で判断すること。スイッチを押して他の家事をこなせるので、体感的な時短効果はしっかり実感できます。
使えない食材がある?NG食材リスト
自動調理器は万能に見えても、実は「向いていない食材」や「NG料理」が存在します。特に圧力調理対応モデルでは、泡立ちやすい食材(豆乳、牛乳、クリームなど)を使うと、吹きこぼれや詰まりの原因になります。また、油分の多い揚げ物や炒め物、焼き目をつけたいステーキなどは基本的に不向きです。
メーカーによっては、「麺類」「卵」「魚介類の一部」なども非推奨とされています。例えばパナソニックのオートクッカーは235種類のレシピに対応していますが、その中にも「油で炒める系」「衣をつける系」は含まれていません。圧力調理や蒸し調理を中心とした設計だからです。
自動調理器は“煮る・蒸す・茹でる・圧力調理”に強く、“焼く・揚げる・焦がす”には弱い傾向があります。購入前に「何を作りたいか」を明確にしておくと、失敗を防げます。万能調理器というより「煮込み特化型」と理解しておくと良いでしょう。
サイズと置き場所の問題
もう一つ見落としがちなデメリットが「サイズ問題」です。多機能な自動調理器ほど本体が大きく、重量も5〜7kg程度あります。キッチンカウンターやシンク周りにスペースがないと、調理時に毎回出し入れする手間が発生します。また、使用中は蒸気が出るため、吊戸棚の下に置くと結露や変色の原因にもなります。
レビューでも「炊飯器と併用できない」「調理時に場所を取る」といった声が多く、特に一人暮らしの狭いキッチンでは悩ましい点です。購入前に「置く場所の確保」が必須です。
一方、最近のモデルでは縦型やコンパクト設計のタイプも登場しています。象印やティファールなどは、収納時にフタを反転できるモデルを展開しており、狭いキッチンでも対応可能。購入の際は、「容量」と「本体サイズ」を両方チェックするのが鉄則です。
電気代・消費電力の落とし穴
自動調理器はガスを使わないため安全ですが、そのぶん電力を消費します。電気圧力鍋の消費電力は700〜1000Wが一般的で、調理時間が長い場合は1回あたりの電気代が10〜20円程度になることもあります。頻繁に使うと月数百円〜千円単位で電気代が上がることもあるため注意が必要です。
特に「保温機能」を長時間使うと、じわじわと電気代がかさみます。エコに使うには、保温よりも「調理後にすぐ冷蔵し、食べるときに温め直す」使い方がおすすめです。
ただし、ガスを長時間使うよりは総合的に安く済むケースもあります。電気代が心配な人は、「省エネモード」や「断熱構造の内鍋」を採用しているモデルを選ぶとよいでしょう。最近の製品では効率的な温度制御が進化しており、以前より電力効率はかなり改善されています。
事前準備が必要な料理もある
「材料を入れてボタンを押すだけ」とは言っても、実際は“下ごしらえ”が必要な料理も多いです。たとえば、肉に焼き目をつけたい場合や、野菜の水分を飛ばしたい場合などは、事前にフライパンで処理してから自動調理器に入れる必要があります。また、調味料の分量や順番を間違えると味にムラが出ることも。
特にカレーやシチューのようにとろみをつける料理では、ルウを入れるタイミングに注意が必要です。最初から入れると焦げ付きの原因になるため、調理後に混ぜるのが鉄則です。
つまり、「全自動」とはいえ、下準備の部分は人の手が必要。これを理解しておかないと、「思ったより手間がある」と感じてしまいます。とはいえ、慣れれば数分の作業で済むため、使いこなせば確実に時短効果を実感できるようになります。
デメリットをカバーする!自動調理器の選び方
パーツが少なく洗いやすいモデルを選ぶ
自動調理器の最大のネックである「お手入れの手間」を軽減するためには、パーツ数が少なくて洗いやすいモデルを選ぶことがポイントです。
特に毎日使う人にとって、洗う手間が多いと「結局使わなくなる」というパターンが非常に多いです。
象印のホーロー電気調理なべ「EL-NS23」では、洗うパーツが「内ぶた・ホーローなべ・つゆ受け」の3つだけで完結します。内鍋は焦げつきにくく、においも残りにくいホーロー製。煮込みやスープを作ったあとも、軽く洗うだけでOKです。
一方で、ティファールやアイリスオーヤマの一部モデルのように、蒸気弁や内蓋が複雑な構造だと、毎回分解する必要があり、乾燥にも時間がかかります。
選ぶときは、次の3点をチェックしてみましょう。
-
取り外し可能なパーツが少ないこと
-
パッキン部分が洗いやすいこと
-
食洗機対応の素材であること
これらを満たすモデルは、結果的に長く使える傾向があります。手入れが楽だと「使う→洗う→また使う」のサイクルが続きやすく、宝の持ち腐れを防げます。
自動減圧機能つきで時短を実現
圧力調理をする自動調理器の中で、意外に時間を取るのが「減圧の時間」です。調理終了後、圧力が自然に抜けるまで10分以上かかることも珍しくありません。この待ち時間を短縮してくれるのが「自動減圧機能」です。
たとえば、パナソニックの「オートクッカーNF-AC1000」では、調理が終わると自動的に減圧を開始し、蒸気を安全に排出する構造になっています。これにより、減圧時間が約半分に短縮され、調理完了から食事までの待ち時間を大幅にカットできます。
また、減圧を自動で行うことによって、フタの開閉を誤ってやけどするリスクも軽減されます。特に小さな子どもがいる家庭では、この機能は安心面でも大きなメリットです。
時短家電としての性能を最大限に発揮させるには、「調理時間+減圧時間」で比較するのがコツ。購入時には「減圧にかかる時間」や「自動排気機能の有無」を必ず確認しておきましょう。
家族人数に合う容量を選ぶ
自動調理器選びで失敗しがちなポイントが「容量のミスマッチ」です。大きすぎると置き場所に困り、小さすぎると一度に調理できず不便になります。
象印の調査によると、家庭でよく選ばれているのは3.0〜4.0Lのモデルが中心。
目安としては次の通りです👇
| 家族人数 | 推奨容量 | 料理の量の目安 |
|---|---|---|
| 1〜2人 | 2.0〜2.5L | カレー2〜3皿分 |
| 3〜4人 | 3.0〜4.0L | カレー5〜6皿分 |
| 5人以上 | 4.0L〜 | 作り置きにも対応 |
一人暮らしで「作り置きをしたい」人は、あえて大きめを選ぶのもおすすめ。作った料理を小分け冷凍しておけば、平日の食事準備がグンと楽になります。
また、「家族でシェアする」「お弁当用も作る」など、生活スタイルに合わせて少し余裕を持たせるのがベストです。
なお、大容量モデルはサイズが大きい傾向にあるため、購入前にキッチンの設置スペースをしっかり測っておくと失敗しません。
予約・保温機能の有無を確認
「朝セットして夜帰宅したら完成している」という使い方をしたいなら、予約機能と保温機能の有無は要チェックです。
象印やパナソニックの最新モデルでは、最大12時間前から予約調理が可能なものも登場しています。これなら、出勤前に材料を入れておくだけで、帰宅時には温かい夕食が完成します。
ただし、すべての機種に予約機能がついているわけではありません。特に低価格モデルでは、省略されていることも多いので注意が必要です。
また、保温機能にも「自動切り替えタイプ」と「手動設定タイプ」があります。
保温時間が長いと電気代が気になるところですが、最近の製品では断熱構造が進化しており、電力消費を抑えながら温度をキープできるようになっています。
特におすすめなのが「タイマー+自動保温+再加熱」まで対応しているモデル。これなら、食事のタイミングが家族でバラバラでも、いつでもできたての味を楽しめます。
スマホ連携など最新機能もチェック
近年の自動調理器は、スマート家電化が急速に進んでいます。パナソニックの「キッチンポケットアプリ」では、スマホからレシピを検索して本体に送信したり、調理状況をリアルタイムで確認したりすることができます。
これにより、「メニュー選び」「材料の確認」「作り方の説明」をすべてスマホ上で完結できます。また、クラウド更新により新しいレシピが自動で追加されるため、飽きずに長く使えるのも魅力。
さらに、IoT対応モデルでは外出先から操作できるものも登場。帰宅時間に合わせて調理をスタートできるため、忙しい共働き家庭にもぴったりです。
こうした機能は価格を押し上げる要因にもなりますが、「毎日使う前提」で考えれば、十分に価値のある投資です。
料理が苦手な人ほど、レシピ連携や自動メニュー更新が便利。機械が苦手な方でも、タッチ操作で直感的に使えるよう設計されています。
実際に後悔した人のリアルな声まとめ
「思ったより置き場所に困る」
自動調理器を買って最初に直面する現実が「置き場所問題」です。
購入前は「炊飯器くらいのサイズかな?」と思っていた人が多いのですが、実際には高さ30cm・奥行30cmを超えるモデルも多く、炊飯器と同時に置くのが難しいケースがよくあります。
特に圧力式タイプは内部にモーターや安全弁があるため、構造的にどうしても高さが出てしまいます。また、使用中は蒸気が出るため、棚の下や壁際に置くと結露の原因にも。
SNSでは「調理中に棚の下がびしょびしょになった」「湯気で壁紙が変色した」という声も見られます。設置スペースに余裕がないキッチンでは、蒸気が逃げる位置を確保して使う工夫が必要です。
最近は「蒸気口が横向き」や「排気方向を選べる」モデルもあるので、キッチン環境に合う構造を選ぶのがポイント。コンパクトさよりも「安全に使える配置」を優先しましょう。
「調理後の掃除が想像以上に手間」
実際の利用者の口コミで最も多い不満が「洗い物が多い」「細かい部分の掃除が大変」という声です。
調理後は内鍋だけでなく、フタの裏のパッキン、蒸気弁、内ぶたなども汚れが付着します。特に煮込み料理を作ったあとは油分やルウの粘度が高く、スポンジで何度か洗わなければ落ちないこともあります。
「使い終わったあとに分解して洗って乾かすのが面倒」「パーツを紛失しそう」という意見もあり、これが理由で“使う頻度が減った”というユーザーも少なくありません。
この悩みを防ぐには、「パーツの少なさ」「食洗機対応」「ホーロー鍋構造」の3点をチェックするのが重要です。象印のホーローなべモデルは、蓄熱性が高く洗浄も簡単で、実際に“手入れのしやすさ”で高評価を得ています。
使うたびに“後片づけがストレスにならない”ことが、自動調理器を長く愛用できるかどうかの分かれ道です。
「カレーを一度に作れない」
「自動調理器を買ったのに、家族4人分のカレーが入りきらない!」という声も多くあります。
容量3.0Lと書かれていても、実際に調理できるのは“満水の約6割”まで。圧力鍋構造のため、内部に空間を残さないと安全に圧力をかけられない設計になっています。つまり、3.0Lモデルでは約1.8L分しか調理できません。
4人以上の家庭だと「足りない」「2回に分ける必要がある」という結果に。特にカレーやシチューなど、具材が多い料理は容量不足を感じやすいです。
象印の解説でも、「人数が2人以下なら3.0L未満、3人以上なら3.0L以上の製品が理想」と明言されています。購入時には“総容量”ではなく、“調理容量”で判断することが大切です。
また、スープやシチューなど水分の多い料理をよく作る人は、容量に余裕をもたせておくと失敗しません。サイズの見極めを誤ると、せっかくの便利機能が活かせないという後悔に繋がります。
「ブレーカーが落ちた!」
意外と見落としがちなトラブルが「電源まわり」です。自動調理器は消費電力が700W〜1000Wと高く、電子レンジやトースターと同じコンセントから電力を取ると、ブレーカーが落ちる可能性があります。
特に築年数が古い住宅やアパートでは、1口コンセントあたりの許容量が低いことが多く、「レンジ+調理器+炊飯器」で同時使用した瞬間に電源が落ちた、というケースが少なくありません。
安全に使うためには、専用コンセントでの利用が基本です。延長コードやタコ足配線もNG。発熱やショートの危険性があります。
最近のモデルでは「省電力モード」や「保温時の出力調整機能」が搭載されており、無駄な消費電力を抑えられるようになっています。購入前には“消費電力(W数)”を確認し、家の配線容量(A)と合わせてチェックしておきましょう。
「結局あまり使わなくなった」
「最初は楽しくて毎日使っていたけど、1か月後には棚の奥に…」という声も少なくありません。原因の多くは、「メニューが限られている」「洗い物が面倒」「下ごしらえが必要で思ったより時短にならない」といった点です。
また、レシピブックのメニューが自分の好みに合わず、結局カレーや煮物ばかり作って飽きてしまうケースも。特に単機能モデルでは、応用がきかないため「結局鍋でいいかも」と感じる人もいます。
これを防ぐには、「自分の料理スタイルに合うか」を事前に確認することが何より重要です。
・毎日料理を時短したい → 自動攪拌機能付きモデル
・週末に作り置きしたい → 大容量タイプ
・おしゃれな料理を試したい → 低温・無水調理対応モデル
自動調理器は“使いこなすほど便利になる家電”です。少しの工夫で、後悔家電から“生活を変える相棒”に変わります。
メリットも理解して上手に使うコツ
ほったらかし調理で家事の時短に
自動調理器の最大のメリットは、なんといっても「ほったらかしで料理が完成する」ことです。
材料と調味料を入れてボタンを押すだけで、カレーやシチュー、角煮などの手間のかかるメニューも自動で仕上げてくれます。
火を使わず、タイマー設定や自動攪拌(かくはん)機能がついているモデルなら、焦げつきや吹きこぼれの心配もゼロ。
たとえば、パナソニックの「オートクッカーNF-AC1000」では、食材を自動でかき混ぜながら調理してくれるので、途中で様子を見る必要がありません。
この“目を離せる時間”が、主婦や共働き家庭には大きな助けになります。
仕事の合間や育児中でも料理が進むので、時間の使い方がガラリと変わるのです。
「調理=拘束時間」という常識を変えたのが、自動調理器の最大の革命といえます。
栄養を逃さない加熱制御
自動調理器は“時短”だけでなく、“健康的な料理”を実現できるのも大きな強みです。
象印やティファールの多くのモデルでは、無水調理や低温調理に対応しており、野菜や肉の栄養素を逃しにくい構造になっています。
無水調理は、水を加えずに食材の持つ水分で加熱するため、ビタミンやミネラルが壊れにくく、野菜本来の甘みやうま味が引き立ちます。
また、低温調理機能を使えば、鶏ハムやローストビーフをしっとりジューシーに仕上げることができます。
特に小さな子どもや高齢者のいる家庭では、「やわらかく消化しやすい料理」を簡単に作れる点が高く評価されています。
さらに、加熱時間と温度をマイコンで自動制御するため、焦げつきや煮崩れが起きにくいのもポイント。
忙しくても“栄養を考えたごはん”が作れるのは、自動調理器の隠れた実力です。
子育て家庭や高齢者におすすめ
子育て中の家庭では、キッチンに長時間立つことが難しい時期もあります。
そんなときに自動調理器があると、子どもの世話をしながら安全に調理できるのが大きなメリット。
火を使わないため、小さな子どもがそばにいても安心。調理中に目を離しても問題ないので、離乳食づくりにも重宝します。
象印のモデルでは「やわらか煮込み」や「取り分け幼児食」など、家族全員に対応できるレシピが多数搭載されているのも特徴です。
また、高齢の方にとっても自動調理器は安全な調理家電です。
手元が不安定になっても火を使わないため事故のリスクが少なく、ボタン操作だけで調理ができるシンプル設計のモデルも多くあります。
家族のライフステージを問わず活用できるのが、自動調理器の強み。まさに“家族に寄り添う調理家電”です。
安全面とエコ面のメリット
「電気で調理する=火を使わない」ことは、安全面だけでなく環境面のメリットにもつながります。
ガスのように無駄な熱が逃げないため、効率よく加熱でき、エネルギーロスを最小限に抑えます。
また、圧力調理によって短時間で加熱が完了するため、総消費電力量も抑えられます。
1回の調理にかかる電気代はおよそ3〜10円程度。長時間煮込みに比べれば、トータルでは省エネです。
安全性も高く、圧力機能付きモデルでは「ロック機構」「安全弁」「自動減圧」などが備わっており、加熱中に誤ってフタを開けることはできません。
小さなお子さんや高齢の方がいる家庭でも安心して使えるのが魅力です。
環境と安全、どちらも配慮された“次世代型の家電”として、自動調理器はこれからますます普及していくでしょう。
結論:デメリットより“使いこなし”が重要
ここまで見てきたように、自動調理器には確かにデメリットも存在します。
しかし、それを上回るメリットや工夫次第で解決できるポイントが多いのも事実です。
たとえば、「洗うのが面倒」ならパーツが少ないモデルを選ぶ。
「思ったより時間がかかる」なら自動減圧付きの機種を選ぶ。
「置き場所がない」なら縦型や小型タイプを検討する。
つまり、自動調理器は“選び方”と“使い方”次第で快適度が大きく変わる家電なのです。
家族構成やライフスタイルに合わせて選び、正しい知識を持って使えば、
デメリットはほとんど気にならなくなります。
「時短」「安全」「健康」「節約」──この4つを叶える調理器具。
自動調理器は、もはや“便利グッズ”ではなく、“生活を変える主役”になりつつあります。
賢い購入方法とおすすめモデル
初心者向け:シンプル操作タイプ
初めて自動調理器を使うなら、「操作がシンプルでお手入れが簡単なモデル」がおすすめです。
特に料理が苦手な方や機械操作に慣れていない方には、ボタン数が少なく、調理モードが明快なものが使いやすいです。
たとえば、象印の「STAN. EL-KA23」シリーズは、温度と時間を自動調整してくれる設計で、操作はたったの2ステップ。「材料を入れて、ボタンを押すだけ」で完成します。
また、洗うパーツは3つだけ。ホーロー製の内なべはにおい移りが少なく、食洗機にも対応しているため、初めての方でも扱いやすいのが魅力です。
さらに、無水調理・スープ・煮込み・デザートといった“失敗しにくい定番メニュー”が豊富。
毎日少しずつ使いこなしていくうちに、自然とレパートリーが広がっていく設計になっています。
初めて買うなら、“使いこなす”よりも“飽きずに使い続けられる”ことを重視するのがポイントです。
家族向け:同時調理・大容量モデル
4人以上の家庭や作り置きをよくする家庭には、「大容量タイプ」または「同時調理対応モデル」が最適です。
一度に複数品を調理できるため、時間の節約になるだけでなく、洗い物も1回で済みます。
象印の「EL-NS23」は、同時に主菜と副菜を作れる“パック調理”機能を搭載しています。
専用ホルダーを使って2つの料理を同時に調理できるので、カレーと副菜の煮物など、夕食全体をワンオペで完成させることが可能です。
また、容量4.0Lクラスのモデルなら、カレーを約6〜8皿分まとめて作れます。
大人数の家族でも1回の調理で完結するため、時間もエネルギーも節約できます。
ファミリー向けを選ぶときは、次の3点を確認しましょう。
-
調理容量が3.5L以上あること
-
同時調理または無水調理に対応していること
-
保温・予約機能が搭載されていること
忙しい家庭ほど、この3要素が時短と満足度を大きく左右します。
料理好き向け:無水・低温調理対応モデル
「料理の幅を広げたい」「お店のような一品を作りたい」という方には、無水調理・低温調理対応モデルが断然おすすめです。
無水調理は、素材の旨味を凝縮し、ヘルシーで濃厚な味わいに仕上がるのが魅力。
低温調理は、温度を60〜80℃に保ちながら加熱するため、鶏むね肉のしっとりハムや、ローストビーフ、温泉卵などが失敗なく作れます。
パナソニックの「オートクッカーNF-AC1000」では、これらの調理法に対応しており、プロのような温度管理を全自動で行います。
さらに、スマホアプリ「キッチンポケット」と連携すれば、200種類以上のレシピを選んで本体に送信できるので、料理好きの創作意欲を刺激してくれます。
また、煮込み・炒め・蒸しを組み合わせた複合調理も可能。
「煮込むだけじゃ物足りない」という方にこそぴったりの、上級者向けモデルです。
レンタルで試すという選択肢
「気になるけど、買って後悔したくない…」という人におすすめなのが、家電レンタルサービスです。
Rentio(レンティオ)などでは、象印やパナソニック、アイリスオーヤマの人気自動調理器を1週間からレンタルできます。
実際に自分のキッチンで試せるため、「サイズ感」「操作性」「味の仕上がり」などを体感してから購入を決められるのが大きなメリット。
「思っていたより大きかった」「思ったより音が静か」など、レビューではわからないリアルな感覚を確かめられます。
レンタル後にそのまま購入できるプランもあるので、無駄なく試せるのも魅力です。
高価な家電だからこそ、“お試し期間”を設けることで満足度の高い選択ができます。
長く使うためのメンテナンス術
せっかく便利な自動調理器も、メンテナンスを怠ると性能が落ち、寿命が短くなってしまいます。
長く快適に使うためには、以下のポイントを意識しましょう。
-
使用後すぐに内鍋を洗う
→ 熱いうちに軽くすすぐと汚れが落ちやすいです。 -
週1回はパッキンと圧力弁を分解清掃
→ 蒸気口に汚れが詰まると加圧にムラが出る原因に。 -
内ぶた・ゴム部品は定期的に交換
→ 劣化すると密閉性が落ち、調理時間が伸びます。 -
保管時はフタを開けて湿気を防ぐ
→ カビ・においの発生を予防できます。 -
専用洗浄モードがある場合は月1回活用
→ 内部の油汚れを自動で除去してくれます。
これらを守るだけで、3年〜5年以上快適に使えるケースも珍しくありません。
“お手入れの習慣化”が、デメリットを最小化し、快適な自動調理ライフを長く楽しむ秘訣です。
まとめ
自動調理器のデメリットは、「お手入れ」「サイズ」「時間」「容量」といった物理的な制約が中心です。
しかし、それぞれに対策があり、選び方と使い方を工夫すれば、むしろメリットのほうが大きくなります。
調理の手間を減らし、健康的な食事を簡単に作れる自動調理器。
上手に選べば「後悔する家電」ではなく、「暮らしを変える家電」になります。
忙しい現代人こそ、毎日の料理を“もっと自由に、もっと楽しく”してくれるこの家電を活用してみてください。