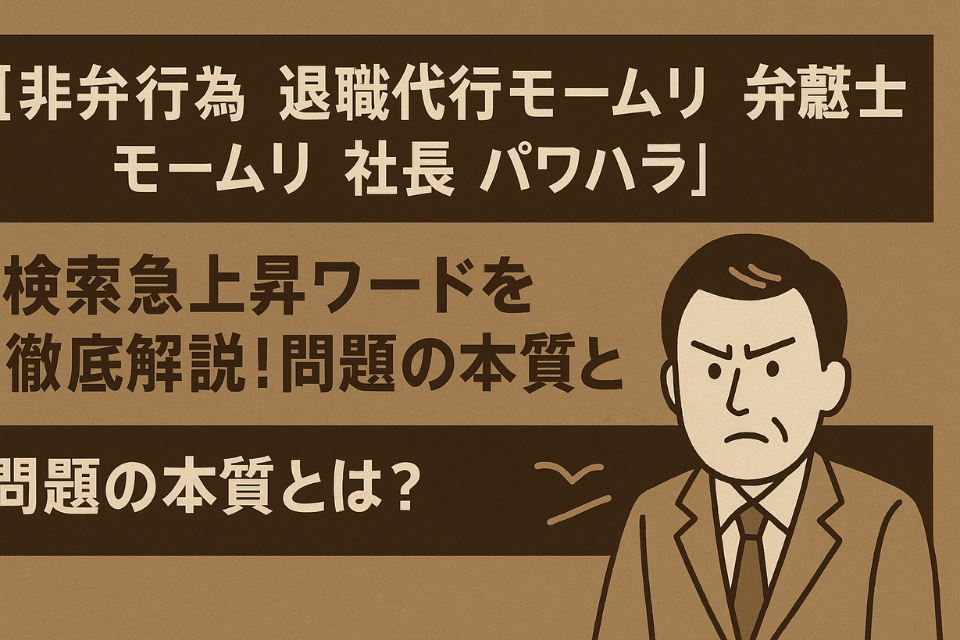「退職代行を使えばすぐ辞められる!」と、若者を中心に人気を集めてきた退職代行サービス。
しかし、2025年10月、業界最大手の「退職代行モームリ」が警視庁による家宅捜索を受け、弁護士法違反の疑いが報じられました。
さらに、社長によるパワハラ問題や、社員自身が退職代行を使っていたという衝撃の事実も発覚。
本記事では、「非弁行為」「退職代行モームリ 弁護士」「モームリ 社長 パワハラ」といった注目ワードの意味や背景、今後の影響について、わかりやすく解説します。
モームリと非弁行為:なぜ問題になっているのか?
非弁行為とは?中学生でもわかる超入門
「非弁行為(ひべんこうい)」という言葉は、普段あまり聞きなれないかもしれません。でも、実はとても大事な意味を持っています。簡単に言うと、法律のトラブルをお金をもらって他人の代わりに解決しようとすることは、弁護士にしか許されていないというルールがあります。これを破ると、法律違反=犯罪になるんです。
たとえば、友だちが先生とけんかして「代わりに言いに行って!」とお願いされて、そのお礼にゲームソフトをもらったとします。これを大人の世界でやると「非弁行為」にあたることがあるんです。
札幌弁護士会の資料によると、非弁行為とは「弁護士資格のない人が、お金をもらって他人のトラブルに首を突っ込むこと」と定義されています。だから、いくら「助けたい」という気持ちがあっても、資格がなければダメなんです。
退職代行モームリにかけられた「非弁行為」の疑いとは
退職代行モームリは「本人に代わって会社に退職の意思を伝える」というサービスで、一見すると便利に見えます。しかし問題は、そのサービスの範囲を超えて、残業代の請求やパワハラの慰謝料など、法律的な交渉まで行っていた可能性があるということです。
本来、こうした交渉は弁護士の仕事で、法律の専門知識が必要です。モームリがそれを行っていたとしたら、「非弁行為」に該当する可能性が高く、警視庁はその疑いで家宅捜索に踏み切りました。
弁護士法第72条とは?退職代行での適用ケース
弁護士法第72条は、弁護士でない者が法律事務を報酬目的で行うことを禁止しています。この「法律事務」には、退職交渉や残業代の請求などが含まれます。
モームリがこれを知らずにやっていたとは考えにくく、元従業員の証言では「違法行為を外に漏らさないように言われていた」との話も出ています。このような内部告発が捜査のきっかけになったとも言われています。
違法リスクが生まれる仕組みと利用者の不利益
利用者からすれば「お金を払ってお願いしてるのに、なんで違法なの?」と思うかもしれません。でも、非弁行為は法律知識のない人が交渉することで、本来もらえるはずの退職金がもらえなかったり、逆に会社から損害賠償請求されるリスクもあります。
毎日新聞の報道によれば、実際にそうしたトラブルに巻き込まれたケースも出てきています。だからこそ、専門家である弁護士でなければ、こうした仕事はしてはいけないのです。
今後の業界への影響とは?弁護士の立場から
この件は、退職代行業界全体にも大きな影響を与えるでしょう。東京弁護士会も2024年から警鐘を鳴らしており、弁護士の向原栄大朗氏は「法律の仕事は医者の手術と同じくらい慎重さが必要」と語っています。
今後、退職代行サービスは「弁護士型」にシフトするか、もしくは法的業務に一切関与しない「伝言型」に分かれていく可能性が高いです。
「退職代行モームリ 弁護士」検索急増の理由
モームリが提携していた弁護士とは誰?
モームリは運営会社が弁護士事務所と提携していたとされています。しかし、その内容が問題です。報酬を得るために、依頼者を特定の弁護士に「あっせん」していた場合、それ自体が非弁行為に該当します。
提携先の弁護士事務所も今回の家宅捜索を受けており、法的責任が問われる可能性もあります。
弁護士あっせん疑惑と報酬の仕組み
特に問題視されているのは、モームリが退職代行の過程で弁護士を紹介し、その報酬の一部を受け取っていたのではないかという疑惑です。これは、弁護士法で禁止されている「報酬目的の周旋(あっせん)」にあたります。
こうした仕組みが明るみに出れば、モームリだけでなく、同様のモデルで運営していた他社も捜査対象となるかもしれません。
「弁護士が関われば安心」は本当か?
「弁護士が関わっていれば安心」と考える人は多いですが、それは正しい弁護士の関与であることが前提です。弁護士法違反の疑いがあるような提携の仕方では、利用者が守られるどころか、逆にトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
安心のためには、消費者自身が「どのような仕組みで弁護士が関与しているのか?」をしっかり確認することが必要です。
警視庁の家宅捜索と弁護士事務所の関係
2025年10月、警視庁が強制捜査に踏み切った背景には、弁護士との提携実態を明らかにしたいという狙いがあったと見られています。報道では、弁護士事務所が紹介料を受け取っていたという証言もあり、事実であれば重大な問題です。
このように、モームリのケースは単なる違法行為ではなく、弁護士を巻き込んだ構造的な問題があるのです。
正しい退職代行の選び方:弁護士型と一般業者型の違い
退職代行には大きく分けて以下の3種類があります:
| タイプ | 法的交渉の可否 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 弁護士型 | 〇 | 法的交渉も可能 | 費用が高め |
| 労働組合型 | △ | 一部交渉が可能 | 組合員になる手続きが必要 |
| 一般業者型 | × | 料金が安い | 非弁リスクが高い |
「モームリ 社長 パワハラ」報道の裏側
元社員の証言「社員全員の前で…」とは?
退職代行モームリの問題で特に注目されているのが、社長によるパワハラです。元従業員の証言によると、「社員全員がいる場で大声で叱責された」「人格を否定するような発言が日常的だった」といった事例が複数報告されています。
こうした行為は、いわゆる「公開処刑型パワハラ」とも呼ばれ、精神的なダメージが非常に大きいとされています。被害にあった元社員の中には、「精神的に限界だった」「泣きながら会社を出た」という人もおり、その深刻さがうかがえます。
しかも、これらの証言は複数人から同じ内容が出てきており、単なる個人の感情ではなく、組織全体に根付いた問題である可能性があります。
会社内部のブラックな実態とは何か
モームリの社内体制については「辞める社員が続出している」「会社の雰囲気がピリピリしていた」との声もあります。文春オンラインの記事では、実際に退職代行を使って辞めた社員がいたことも報じられています。
また、社員に対して「口外しないよう強く言われた」など、情報を外に漏らさないようプレッシャーをかけていたことも明らかになっており、いわゆる「ブラック企業」の典型的な体質だったと考えられます。
中でも特筆すべきは、退職代行サービスを提供している会社の社員自身が、他の退職代行業者を使って辞めていたという衝撃の事実です。これは、「自分たちのサービスには頼れなかった」という深刻な矛盾を象徴しています。
社長の経歴と企業文化が問題を生んだ?
モームリを運営する株式会社アルバトロスの社長・谷本慎二氏は、かつてテレビ番組などでも「カリスマ経営者」として紹介されていた人物です。しかし、その表の顔とは裏腹に、社員への高圧的な態度や業務の強制など、ブラック体質を指摘する声が絶えませんでした。
また、社長の一言が絶対という企業文化があったことも元社員の証言からわかっています。こうした「ワンマン経営」や「トップダウンすぎる組織」は、社員が自由に意見を言えない空気を作り、結果的にパワハラの温床になることがあります。
これにより、社内での適切な相談ルートや内部告発制度も機能せず、不満が蓄積していったと考えられます。
「パワハラ体質」と離職率の関係
一般的に、職場の離職率が高い企業には、何らかの「構造的な問題」があることが多いです。モームリの場合も、設立から3年ほどで3万件の退職代行を扱うほど急成長を遂げた一方で、内部の人材が定着しないというギャップが見られました。
特にパワハラが原因で辞めた社員は、モームリに対する不信感だけでなく、退職代行業界全体への不信にもつながっています。
ある意味、退職代行の“裏の顔”が浮き彫りになったとも言える今回の事件は、業界に対する信頼を大きく揺るがすことになりました。
利用者ではなく“中の人”が退職代行を使った衝撃
最も衝撃的なのは、モームリの社員自身が退職代行を使って辞めていたという点です。自社のサービスではなく、他社の退職代行を使ったということは、「自分たちのサービスには信頼がない」と自覚していた可能性もあるわけです。
この事実は、多くの利用者や業界関係者にとっても驚きだったでしょう。まさに“退職代行の会社から退職代行で辞める”というパラドックスが、モームリの内部問題の深刻さを象徴しています。
退職代行サービス全体の課題と落とし穴
退職代行とは何か?仕組みをわかりやすく解説
退職代行とは、その名の通り「本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービス」です。会社に直接言いづらい人や、パワハラなどの理由で連絡を避けたい人にとって、便利なサービスとして広まってきました。
通常、退職は民法で「2週間前に通知すればできる」とされています。つまり、基本的には誰でも自由に辞められる権利があります。それでも、実際には「引き止められるのが怖い」「人間関係が気まずい」といった理由から、退職がスムーズにできないケースが多いのです。
そのニーズに応える形で登場したのが退職代行です。しかし便利さの裏には「法律的にどこまでできるか」という明確な線引きが必要です。
非弁行為に該当しやすいポイントとは
退職代行サービスが「非弁行為」として問題視されるのは、本人の意思を伝えるだけでなく、会社と報酬や条件などを交渉した場合です。たとえば:
-
未払い残業代の請求
-
パワハラの慰謝料請求
-
退職金の支払い交渉
-
証明書類の発行催促
-
トラブルの調整・和解案の提示
これらはすべて「法律事務」に該当し、弁護士でない者が行うと弁護士法違反になります。
トラブルを避けたい気持ちで代行サービスを頼んだのに、逆に新たなトラブルを生むこともあり得ます。
契約時に確認すべき3つのチェックリスト
退職代行を選ぶときは、以下のポイントを必ずチェックしてください:
-
サービス提供者は弁護士か?
→ 弁護士でなければ交渉はNGです。 -
実際にどこまでやってくれるのか?
→ 「言伝」だけなのか、書類対応もするのか要確認。 -
料金とサービスの内訳が明確か?
→ 後で追加料金を請求される事例も。
この3つを確認するだけでも、トラブルのリスクは大きく減らせます。
弁護士型・労働組合型・民間型の違い
退職代行には次の3タイプがあります:
| タイプ | 法律交渉 | 主な特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 弁護士型 | ◎ | 法的交渉が可能 | 約3万~6万円 |
| 労働組合型 | ◯ | 組合員の権利として交渉可能 | 約2万~4万円 |
| 民間業者型 | × | 言伝だけのシンプルサービス | 約1万~3万円 |
「安いから」と選んでしまうと、後で「非弁行為」として問題になる可能性もあるため、タイプごとの違いを理解して選びましょう。
利用者が後悔しないための選び方
失敗しない退職代行選びのポイントは、「価格」ではなく「信頼性」です。口コミや評判、運営会社の実態、弁護士との関係性などを事前にしっかり調べましょう。
そして何より、「自分がどこまでのサポートを必要としているのか」を明確にすることが大切です。単に退職の意思を伝えたいだけなら民間型で十分かもしれませんし、パワハラや未払い金の交渉が必要なら弁護士型を選ぶべきです。
今後どうなる?モームリ事件がもたらす未来
モームリに対する今後の捜査と法的対応
2025年10月、警視庁は退職代行モームリを運営する企業に対し、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで家宅捜索を実施しました。この捜査の行方は、今後の業界のあり方を左右する重要なポイントとなるでしょう。
仮に捜査の結果、モームリ側に違法行為が認定されれば、刑事罰の対象になる可能性もあります。また、業務停止命令やサービスの閉鎖、さらには提携していた弁護士事務所に対しても処分が下されることが予想されます。
この事件は単なる「一企業の問題」ではなく、退職代行業界そのものの透明性や信頼性が問われる転機となるでしょう。
同様の退職代行サービスにも影響拡大か?
モームリは業界最大手であり、知名度も高い企業です。そのため、今回の問題は他の退職代行サービスにも波及する可能性があります。特に、同じように弁護士と提携している企業は、その提携内容が適法かどうかを今一度見直さざるを得なくなるでしょう。
また、利用者からの不信感も高まることが予想され、サービスの利用をためらう人が増えるかもしれません。信頼回復のためには、業界全体でガイドラインを作るなどの対応が必要になりそうです。
弁護士会や専門家の見解まとめ
東京弁護士会や札幌弁護士会では、以前から退職代行に関する「非弁行為」のリスクについて警鐘を鳴らしてきました。実際、2024年には注意喚起文書も公開されており、その中で「パワハラ慰謝料や残業代の交渉は非弁行為に該当する」と明言しています。
非弁行為に詳しい弁護士の間では、「業界全体がグレーな領域を見直す必要がある」との声が強まっています。また、今後は行政や弁護士会と連携した指導や取り締まりが強化される可能性もあります。
企業側の受け止めと対策の動き
一方で、退職代行サービスを利用される企業側にも変化が起こると予想されます。今までは「代行からの連絡には応じない」というスタンスの企業もありましたが、今後は法的に適切な対応を求められるようになるかもしれません。
また、企業の人事部門では、社内の退職手続きをより丁寧に行うことや、社員の不満を早期にキャッチする体制づくりが重要になります。退職代行に頼られないような職場環境づくりが、企業の新たな課題となるでしょう。
利用者・求職者に必要な心構え
今回の件を受けて、退職代行を検討している人や現在利用している人にとっては、「サービス選びの基準を見直す」ことが最も重要です。
料金の安さだけで選ばず、「法的に安全な運営をしているか」「弁護士の関与が明確か」などを事前に調べましょう。SNSやレビューサイトだけに頼らず、運営会社の公式ページや実際の相談事例など、複数の情報を参考にするのが賢明です。
また、万が一トラブルに巻き込まれた場合は、迷わず弁護士に相談することも大切です。安心して退職できる環境は、自分自身で守る時代になってきています。
まとめ
退職代行モームリの問題は、単なる一企業の不祥事ではなく、退職代行という新しいサービスの「法的限界」と「倫理的課題」を私たちに突きつけた事件でした。
特に「非弁行為」という法律違反の可能性や、社長によるパワハラ体質などは、企業としての信頼を大きく損なうものでした。さらに、社員自身が退職代行を使って辞めていたという事実は、業界の構造的な問題を象徴しています。
今後、退職代行サービスを利用する人は、サービスの“手軽さ”だけでなく“合法性”や“信頼性”をしっかりと見極める必要があります。法に守られたサービスを選ぶことが、最終的に自分自身を守ることにつながります。
退職は人生の大きな転機。その選択肢が増えることは良いことですが、その分、私たちも賢くなければいけません。