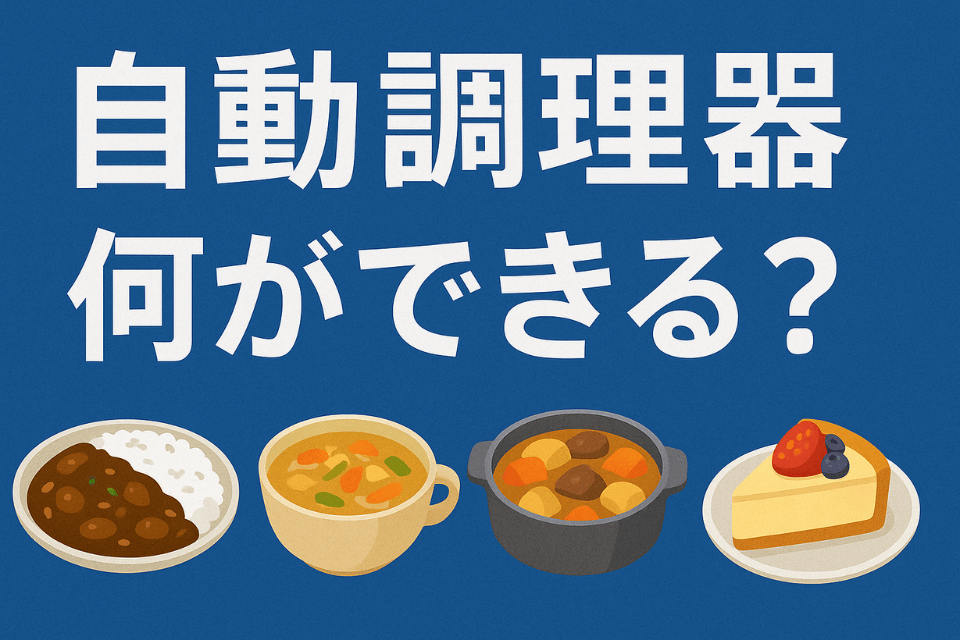「毎日のごはん作りが面倒…」「料理の時間をもっと短縮したい…」
そんな悩みを抱える方におすすめなのが、自動調理器。最近では、材料を入れてボタンを押すだけで、カレーからスイーツまで何でも作れてしまう優れものが続々と登場しています。
でも実際、「自動 調理 器 何 が できるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、自動調理器の機能やできる料理、選び方、実際の活用法までを徹底解説!
初心者でもすぐに使いこなせる情報満載でお届けします。
これを読めば、自動調理器の魅力と可能性が丸わかり!忙しい毎日をぐっとラクにするヒントが見つかりますよ。
自動調理器で何ができる?基本機能と活用例
自動調理器ってどんな家電?
自動調理器とは、材料と調味料を入れてボタンを押すだけで、料理がほぼ自動で完成する便利な家電です。特に忙しい毎日を過ごす家庭や、料理が苦手な方、共働き世帯にとって救世主とも言える存在です。火加減の調整や混ぜる作業を自動で行ってくれるため、キッチンにずっと立っている必要がありません。
最近の製品では「無水調理」や「低温調理」、「予約調理」などの機能が搭載されており、放っておいてもプロのような仕上がりに。例えば朝セットしておけば、夕方には温かいカレーが完成しているという使い方もできます。
また、安全性も高く、火を使わないため小さなお子さんがいても安心。特に「圧力機能つき」のタイプは短時間で味がしみ込むので、煮込み料理も得意です。忙しくても栄養バランスの良い食事を手軽に準備できるのが大きな魅力です。
できる料理の種類はこんなに多い!
自動調理器の魅力は、その対応できるメニューの豊富さにあります。例えばパナソニックのオートクッカーでは、なんと235種類以上のメニューに対応しています。カレーやシチューはもちろん、炒飯、麻婆豆腐、スープ、パスタ、蒸し物、さらにはスイーツやソース作りまで対応可能です。
電気圧力鍋タイプでは、骨付き肉を使った煮込みや、魚の煮付けも短時間でしっとり柔らかく仕上がります。スロークッカータイプの製品では、じっくり煮込むことで食材の旨味を引き出せるので、豚の角煮やビーフシチューなどにもおすすめ。
また、スイーツも得意な機種があり、プリンやケーキ、甘酒などが簡単に作れるのも魅力です。レパートリーの広さに驚く人も多く、「これ一台でここまでできるの?」と感動する声が多いのも納得です。
時短と手間なしが叶う理由とは?
自動調理器は、なぜここまで「時短」「手間なし」を実現できるのでしょうか。その理由は、調理工程をすべて自動化しているからです。たとえば、煮込み料理で必要な「火加減の調整」「混ぜる作業」「加熱時間の計測」などを全て家電が担当してくれるので、私たちは「材料を切って入れるだけ」で済みます。
特に予約機能付きのモデルでは、朝に材料を仕込んでおけば、夕方には料理が完成しているため、帰宅してからバタバタすることもありません。さらに、保温機能がついていれば、食事の時間がずれても温かいまま食べることができてとても便利です。
また、パナソニックなど一部の製品には「炒め→煮込み」など複数工程を自動で切り替える機能もあり、まさに"ほったらかしで本格料理"が可能。毎日の料理を短時間で、しかも失敗なくこなせることが、最大の強みといえるでしょう。
自動調理の仕組みと安全性について
自動調理器は、センサーやマイコン制御を活用して、加熱時間や温度を自動で調整します。これにより、ふきこぼれや焦げつきといったトラブルを防ぎつつ、安定した調理ができます。火を使わず電気で加熱するため、ガス漏れや火災の心配がないのも大きな安心材料です。
また、圧力タイプの調理器には、安全弁やロック機構が装備されており、調理中はフタが開かない構造になっています。調理終了後に圧力が抜けてから開けることで、やけどなどのリスクを回避しています。
一部の機種では、加熱中に自動でかき混ぜる「攪拌機能」まで搭載しており、炒め物やリゾットなども焦げ付きにくく、手間をかけずに美味しく仕上げることが可能です。使い方もシンプルで、タッチパネル操作やスマホ連携で誰でも扱いやすい設計になっており、初心者でも安心です。
電気代やコスパはどうなの?
「便利なのはわかるけど、電気代が高くつくのでは?」と心配する方も多いですが、実際にはそこまで心配いりません。例えば、1回の調理にかかる電気代は約3〜10円程度と言われており、ガスを使って長時間煮込むよりも安上がりになる場合もあります。
また、一度に多めに作って作り置きすれば、1食あたりのコストはさらに下がります。加えて、外食や中食(お惣菜)の利用を減らすことができれば、月単位で見ると大幅な節約にもつながります。
本体価格は機種によって異なりますが、1万円台のシンプルなモデルから、高機能モデルでも3万円〜5万円程度が相場。長期的に見れば、十分「元が取れる」投資と言えるでしょう。特に、料理の手間と時間を削減できるメリットを考えると、コスパは非常に高いといえます。
人気の自動調理器ではどんな料理が作れるの?
カレーやシチューなどの定番メニュー
自動調理器の代表的な使い道といえば、やはり「カレー」「シチュー」「肉じゃが」などの定番煮込み料理です。特に圧力調理対応のモデルでは、野菜はホクホク、お肉はトロトロに仕上がり、自分で火加減を調整するよりもむしろ美味しくなることも少なくありません。
たとえば、パナソニックのオートクッカーでは、カレーやシチュー専用のコースが用意されていて、材料を入れてメニューを選ぶだけ。炒め→煮込みの工程も全自動で行われるため、まるでプロが作ったような本格的な味になります。
これらのメニューは家庭の食卓に頻繁に登場するので、時間がない平日でもしっかり栄養のあるごはんを用意したいときにぴったり。しかも、自動でかき混ぜもしてくれるため、焦げつく心配もなく、調理中は他の家事や仕事に集中できます。
無水調理や低温調理もおまかせ!
自動調理器の中には、無水調理や低温調理といった「高度な調理法」に対応したモデルもあります。無水調理は、水を加えずに野菜の水分だけで煮込む方法で、素材本来の旨味や栄養を逃さずに調理できるのが特徴です。特にカレーやラタトゥイユ、野菜スープなどにおすすめです。
一方、低温調理では60〜80℃の一定温度でじっくり加熱することで、ローストビーフや鶏ハム、温泉卵など、火加減が難しい料理が失敗なく作れます。しかも、食材がパサつかず、しっとりとジューシーに仕上がるので、お店のような味を家庭で楽しむことができます。
これらの調理法は手動でやると非常に手間がかかりますが、自動調理器なら設定一つでOK。プロの調理技術を再現できる点でも、自動調理器は非常に優秀な家電だといえるでしょう。
ごはん・パスタなど主食もOK
「おかずは作れるけど、ごはんは炊飯器?」と思いきや、自動調理器は主食もおまかせです。炊飯はもちろん、リゾットやパエリア、パスタまで幅広く対応しています。例えば、トマト缶とパスタ、調味料を入れてスイッチを押せば、10〜20分でアルデンテのパスタが完成します。
炊き込みご飯や玄米、雑穀米にも対応したモデルも多く、健康志向の方にもぴったり。特に一人暮らしや忙しい家庭では、ご飯とおかずを一度に調理できる「同時調理」機能があると重宝します。
また、保温機能があるので、炊いたご飯を温かいままキープしておくことも可能。忙しい朝や帰宅が遅くなる日でも、レンジでチンせずにそのまま食卓へ出せるのはとても便利です。
スイーツまで!意外なメニュー例
「自動調理器でスイーツ!?」と驚く方もいるかもしれませんが、実はプリン、ケーキ、甘酒、ぜんざいなどのスイーツも作れるんです。蒸し機能や保温機能を活かせば、手間のかかるデザート作りも失敗なく簡単にできます。
たとえば、材料を混ぜて流し込むだけでなめらかなプリンが完成したり、炊飯器の要領でパウンドケーキやチーズケーキを焼くことも可能です。甘酒は保温モードを使って発酵させることで、自然な甘みが引き出された健康ドリンクとして人気があります。
子どもと一緒に作るデザートタイムにもぴったりで、休日の楽しみとしても◎。料理の幅を広げるだけでなく、「おうち時間の充実」にも一役買ってくれるのが、自動調理器の魅力です。
離乳食・幼児食にも大活躍!
自動調理器は、離乳食や幼児食を作る家庭にも非常におすすめです。柔らかく煮込む必要のある野菜やおかゆ、魚のほぐし煮なども、セットしてスイッチを押すだけ。付きっきりで見ていなくても安心安全に調理が進みます。
特に離乳食初期は少量ずつ、しかも滑らかに仕上げる必要がありますが、無水調理や低温調理を活用すれば、食材の栄養を逃さずふんわり柔らかく仕上がります。また、パナソニックなどの一部モデルでは「取り分け幼児食」レシピが用意されており、大人と同じ材料で子ども用の食事を取り分けることができます。
調理中に他の家事ができるため、育児中のママやパパにとって大きな助けになります。赤ちゃんの成長に合わせて、段階的なメニューにも対応できるので、長く活躍してくれる家電です。
機種選びで差がつく!自動調理器の選び方
圧力あり・なしの違いをチェック
自動調理器を選ぶ際にまず確認しておきたいのが、「圧力機能の有無」です。圧力調理機能があると、通常よりも高温で食材を加熱できるため、短時間で柔らかく煮込むことができます。たとえば、角煮や牛すじ煮込みといった時間のかかるメニューも30分以内で仕上げられることも。
一方、圧力なしのモデルはじっくり加熱することで、素材の旨みを引き出すスロークッカーのような調理が得意。焦げつきにくく、失敗もしにくいので初心者におすすめです。シンプルな設計で価格も比較的手ごろなのも魅力。
調理時間を優先するなら「圧力あり」、手軽さや使いやすさを重視するなら「圧力なし」と、使うシーンに合わせて選ぶのがポイントです。各社公式サイトでは、対応レシピや調理例が紹介されているので、事前にチェックしておくと後悔が少なくなります。
家族の人数で選ぶ容量の目安
自動調理器には、2.0L〜5.0Lとさまざまな容量があります。適切なサイズを選ばないと、「作りすぎた」「足りなかった」「置き場所がない」などのトラブルにつながりがちです。
一般的には、以下の目安が参考になります:
| 人数 | 推奨容量 |
|---|---|
| 1〜2人分 | 2.0L〜2.5L |
| 3〜4人分 | 3.0L〜4.0L |
| 5人以上 | 4.0L以上 |
2人暮らしで1回使い切るタイプの調理をしたい場合は、2.5L程度が便利です。一方、作り置きやお弁当分も含めて調理したい場合は、少し大きめを選ぶと効率的です。
また、容量だけでなく本体のサイズも重要です。特にキッチンの収納スペースに限りがある場合は、寸法を事前に測っておくことで「置けなかった…」という失敗を防げます。
レシピ数と対応メニューを比較しよう
自動調理器の魅力はなんといっても「調理メニューの多さ」です。製品によって搭載されているレシピの種類や数が異なるため、購入前にチェックすることが大切です。
例えば、パナソニックのオートクッカーは235種類以上のレシピに対応しており、煮物・炒め物・蒸し料理・ご飯・パスタ・スープ・スイーツまで幅広く作れます。一方、シンプルモデルでは煮込み中心で、炒めやスイーツには対応していないこともあります。
また、「炒め→煮込み」などの複数工程を自動で切り替えられるモデルや、「スマホアプリでレシピを追加できる」ようなモデルも増えています。自分が作りたいメニューに対応しているかどうか、使い方が簡単かどうかも含めて比較すると失敗がありません。
掃除のしやすさも見逃せないポイント
毎日のように使う家電だからこそ、「お手入れのしやすさ」は見逃せないポイントです。特に、パーツの数や形状によっては、洗い物が面倒に感じて使わなくなってしまうことも。
おすすめは、取り外せるパーツが少ないもの、または食洗機対応のもの。象印のホーロー電気調理なべ「EL-NS23」は、毎回洗うのは内ぶた・ホーロー鍋・つゆ受けの3点だけとシンプル設計で手間いらず。
さらに、内なべが焦げ付きにくい加工になっているかどうかや、フタのパッキンが取り外しできるかどうかも確認しておきましょう。清潔に保てる家電であることは、家族の健康を守るためにも大切です。
スマホ連携や予約機能も重要!
最近の自動調理器には、スマホ連携機能や予約調理機能が搭載されているモデルも増えています。たとえば、スマートフォンアプリからレシピを選んで本体に送信したり、買い物リストを自動生成してくれるといった便利な使い方ができます。
また、予約調理機能があれば、朝出かける前に材料をセットしておけば、帰宅時間に合わせて夕食が完成しているという便利さも。共働き世帯や子育て中の家庭では、特にこの機能の有無が使い勝手を大きく左右します。
一部モデルでは音声アシスタントに対応しているものや、定期的にレシピが追加されるアップデート機能などもあり、今後さらに便利になることが期待されます。長く使う家電だからこそ、最新機能にも注目して選びたいところです。
実際どう?自動調理器のメリットとデメリット
使って実感!時短効果と料理の幅
自動調理器を使い始めて、まず多くの人が驚くのが「とにかく時短になる!」という点です。材料を切って調味料と一緒に入れたら、あとはボタンを押すだけ。加熱時間や火加減の調整を自分でやる必要がないので、その間に他の家事をしたり、子どもと遊んだり、仕事の続きをしたりと、時間を有効活用できます。
特に煮込み料理やスープなど、通常なら1時間以上かかるメニューが、30分程度で完成することも。料理のレパートリーも増え、「普段は面倒で作らなかった煮物や本格的なカレーにも挑戦するようになった」という声も多くあります。
さらに、炒める、煮る、蒸す、焼く、低温調理、無水調理など、調理の幅が広いため、「料理が楽しくなった」という声も。忙しいけれど食事にはこだわりたいという方には、まさに理想的な調理家電といえるでしょう。
手間いらずでも味は本格派?
「自動で作ると味が落ちるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、実際には多くのユーザーが「思った以上に美味しい!」と驚いています。近年の自動調理器はセンサーとマイコン制御の精度が非常に高く、調理時間や温度を細かく調整してくれます。
特に圧力調理に対応したモデルでは、味がしっかり染み込むため、プロが作ったような本格的な味わいに。加えて、火加減や時間を間違えて焦がしたり煮詰めすぎたりする失敗もありません。
また、調味料の分量もレシピ通りにすればOKなので、味のバラつきが少ないのもポイント。家族からの「これ、どうやって作ったの?」という言葉に、ちょっと自慢したくなるかもしれません。
調理中に目が離せる安心感
従来の調理では、鍋につきっきりで火加減を見たり、途中でかき混ぜたりする必要がありました。しかし、自動調理器ならその必要がありません。料理をセットしてスイッチを押せば、あとは放っておくだけ。調理が終われば自動で保温に切り替わるため、焦がしたり吹きこぼしたりする心配もありません。
これは小さな子どもがいる家庭にとって大きなメリットです。調理中に目が離せることで、子どもの世話をしたり、洗濯や掃除を並行して行うことができます。また、共働きの家庭では、朝セットしておけば、帰宅したときには温かい夕食が待っているという生活が実現します。
キッチンにいなくても安全に調理できるという安心感は、家事のストレスを大きく軽減してくれます。
デメリットは「万能ではない」ところ?
便利な自動調理器ですが、もちろんデメリットもあります。一番多いのは「すべての料理が作れるわけではない」という点。たとえば、食材を焼き目をつけてパリッと仕上げたい、繊細な火加減が必要なフレンチなどには不向きです。
また、調理時間自体は短くても、食材の下ごしらえ(切る、皮をむくなど)は自分で行う必要があるため、「全自動」とまでは言えません。機種によっては炒め機能がなかったり、対応しているメニュー数が少なかったりすることもあります。
そして、慣れるまでは「どれくらいの分量が適切か」「味付けはどうするか」といった戸惑いもあるかもしれません。とはいえ、これはどの家電でもあることで、慣れてしまえば自分なりの使いこなしができるようになります。
実際の口コミから見る満足度
実際に自動調理器を使っている人たちの口コミを見ると、その満足度は非常に高いです。SNSやレビューサイトでは「買って良かった家電No.1」という声も多く、「毎日の料理がラクになった」「外食が減って食費が浮いた」といった声も多数見られます。
一方で、「最初はどの機能を使えばいいのかわからなかった」「思ったより大きくて置き場所に困った」という声も。これらは事前にスペックやサイズ、機能を確認しておけば回避できるポイントです。
使い方のコツやおすすめレシピは、メーカー公式サイトやYouTubeなどでも多数紹介されているので、導入後の不安も少なくなっています。総合的に見て、自動調理器は多くの家庭で「生活を変える家電」として定着しつつあると言えるでしょう。
初心者でも安心!自動調理器のおすすめ活用法
1週間使ってみた簡単献立例
自動調理器を初めて使うとき、「何から作ればいいの?」と迷う方も多いはず。そんな方に向けて、自動調理器を活用した1週間の簡単献立例を紹介します。これは実際に自動調理器を使っているユーザーの声をもとに構成した、初心者向けの安心メニューです。
| 曜日 | メニュー例 | ポイント |
|---|---|---|
| 月曜 | 無水カレー+ごはん | 材料を入れて放置でOK。無水で旨みUP! |
| 火曜 | 鶏のトマト煮+バゲット | 煮込み料理で忙しい日でも楽々 |
| 水曜 | さばのみそ煮+味噌汁(別途) | 圧力調理で骨までやわらか |
| 木曜 | 麻婆豆腐+中華スープ | 炒め→煮込みを全自動で実現 |
| 金曜 | チキンライス風リゾット+サラダ | 一皿完結で洗い物もラク |
| 土曜 | スイートポテト+甘酒 | スイーツ&ドリンクも作れる! |
| 日曜 | 牛すじ煮込み+白米 | 圧力でじっくり、休日のごちそうに |
このように、自動調理器があれば平日のご飯はもちろん、週末の特別メニューやスイーツまで対応可能。作り置きも視野に入れると、週末に多めに作っておけば翌週の食事準備もグッと楽になります。
朝セット→夜完成の時短ライフ
忙しい毎日の中で「料理の時間がとれない」「帰ってからバタバタしたくない」という悩みを解決してくれるのが、自動調理器の「予約調理機能」です。朝出かける前に材料と調味料をセットし、帰宅時間に合わせてタイマーを設定すれば、夜には出来たての料理が待っています。
この機能が便利なのは、加熱時間だけでなく、保温まで自動で切り替えてくれること。たとえば、18時に調理が終わるようにセットしておけば、19時に帰宅しても温かいままのカレーが食べられます。
特に共働き家庭や、夕方以降に予定がある日、子どもの送り迎えで忙しい日などには大活躍。調理中の火加減や焦げつきを心配する必要もないので、安心して外出できます。時間のゆとりができることで、夕食後のリラックスタイムもグッと充実しますよ。
同時調理で主菜と副菜を一気に!
「一度に主菜も副菜も作れたらいいのに…」という願いを叶えてくれるのが、最近の自動調理器に搭載されている「同時調理機能」です。例えば、象印の電気調理なべ「EL-NS23」では、専用ホルダーを使うことで、パック調理による2品同時調理が可能です。
主菜は煮込みハンバーグ、副菜はひじきの煮物、といった組み合わせが同時に作れるため、限られた時間の中でもバランスの良い食卓が完成します。これにより、料理の時間を大幅に短縮でき、献立を考える手間も減らすことができます。
しかも、調味料の味が混ざらないようにパック分けされているため、それぞれの料理の味をしっかり楽しめるのも魅力の一つ。忙しいけれど手を抜きたくない…という方に、ぴったりの使い方です。
作り置き&保存にも向いてる理由
自動調理器は、「作り置き料理」との相性が抜群です。一度に多めに調理して、数日に分けて食べることで、毎日の献立作りが圧倒的に楽になります。特にカレー、肉じゃが、煮豆、スープ類などは日持ちしやすく、冷蔵・冷凍保存も可能です。
また、象印のホーロー電気調理なべは、蓄熱性の高い内鍋がそのまま冷蔵保存できる仕様で、翌日再加熱しても風味を損ないません。鍋のまま食卓に出せるデザインも嬉しいポイントです。
作り置きの良さは、「献立を考える手間」「毎回の調理の手間」「片付けの手間」の3つが一気に減るところ。週末に数品をまとめて作っておけば、平日の夕食準備がグンとラクになります。食材の無駄も減り、節約にもつながりますよ。
失敗しないためのポイント5選
便利な自動調理器ですが、いくつかのポイントを押さえておくことで、失敗なく活用できます。
-
取扱説明書とレシピをよく読む
自分の機種で作れるメニューをしっかり把握することが第一歩。 -
食材の切り方に注意
火の通りを均一にするために、指定された大きさに切るのがポイント。 -
材料を入れる順番を守る
下から順に火が通るため、指示通りの順番で入れましょう。 -
調味料は控えめからスタート
自動調理は味が濃くなりやすいことがあるため、最初は薄味で調整。 -
使用後はすぐに掃除をする
お手入れが簡単とはいえ、すぐに洗うことで清潔&長持ち。
これらを意識するだけで、失敗やストレスがグッと減り、自動調理器ライフを快適に楽しむことができます。
まとめ
自動調理器は、忙しい現代人にとってまさに救世主とも言える家電です。「自動 調理 器 何 が できる?」という疑問に対して、本記事では機能の基本から活用方法までを詳しく紹介してきました。
煮物・炒め物・蒸し物・スープ・ごはん・パスタ・スイーツ・離乳食など、1台で作れるメニューは想像以上に多彩。さらに、圧力調理や無水調理、低温調理といったプロ級の調理法まで自動でこなしてくれるため、料理初心者でも簡単に美味しい料理を作れます。
選び方のポイントを押さえれば、自分のライフスタイルにぴったりの1台を見つけられるはず。そして、予約調理・同時調理・作り置きなどを上手に取り入れれば、毎日の家事がもっとラクになり、生活に余裕と笑顔が生まれます。
料理の負担を減らしながら、健康的でおいしい食事を実現できる自動調理器。まさに「ほったらかしでおいしい」が叶う、最強のキッチンパートナーです。